

うつ病(大うつ病性障害)は心の病気の一つであり、慢性的な抑うつ気分や無気力感、興味や喜びの喪失などを特徴とする病気です。
以前と比べて広く社会的に認知されるようになり、当院でも多くの患者様が来院されます。
この病気は、長期的な悲しみ、無気力、および生活の楽しみを失うなどの深刻な症状(抑うつ症状)を引き起こしますが、適切な診断および治療で改善する病気でもあります。
当院では薬物療法だけに頼った医療ではなく、経験豊富な臨床心理士(カウンセラー)による精神療法を含めた複合的な治療を提案します。

うつ病の症状は、大きく分けて精神的な不調と身体的な不調に分類されます。 それぞれには以下のようなものがあります。
その他、ベッドから起き上がれない、ふわふわ(浮遊感)、めまい、頭痛、全身痛などの多彩な身体症状を呈することがある。
うつ病では、主としてセロトニン、ノルアドレナリン、ドーパミンの3つの脳内神経伝達物質の機能が低下することで、不安、憂鬱気分、意欲の低下、興味関心の低下などの中核症状が出現すると考えられています。
これらの低下の原因はひとつではなく、以下のような複数の要因が絡み合って発症することがわかっています。
ひとつは環境的な要因で、家庭内でのトラブル、職場でのストレス、大切な人との離別といった辛い出来事以外にも、昇進や結婚といった本来喜ばしい出来事など、環境の大きな変化で発症することがあります。
また本人の性格的な要因も挙げられます。
具体的には生真面目、完璧主義、義務感が強いといった性格の方はストレスを受けやすく発症しやすいことが知られています。
その他にも遺伝的な要因、他疾患の合併(糖尿病などの生活習慣病、甲状腺機能低下症、がんなど)、薬剤による副作用などが知られています。
これらの原因に合わせた適切な治療を行うことが重要です。
うつ病は、上に挙げたようさまざまな症状(抑うつ症状)を引き起こしますが、国際的な診断基準(DSM-5)によって以下のように定められています。
ただし、うつ病の発症には、糖尿病などの生活習慣病や甲状腺機能低下症など、他疾患が合併する場合も多く、上記項目の確認以外にも、血液検査などが必要な場合もあります。
また、躁うつ病(双極性障害)や持続性気分障害(気分変調症)といったその他の気分障害との鑑別も難しいため、自己診断を行わず、まずは医師による正確な診断を受けることが重要です。

うつ病の治療には、十分な休息の他、薬物療法、精神療法などが挙げられます。
どれかひとつではうつ病を治療することは難しく、症状や状態に合わせてこれらの治療を組み合わせていくことが重要です。
十分な睡眠時間を確保し、適度な運動を取り入れ、身体面の回復を図ることは精神面の安定化にも大きくつながります。
また場合によっては休職を検討する、人間関係を見直すなど、自身の生活環境を整えることが重要です。
特にうつ状態が深い場合は、休職せざるを得ない場合もあります。
まずは一度受診していただき、本当に休職が必要な状況か、一緒に相談させていただけたらと思います。
休職中は遠出などせず、体を休めることに専念しましょう。
復帰については、主治医と相談しながら段階的に行い、復職前には職場や上司とのコミュニケーションを密にし、適切なサポートを受けることが重要です。
また、職場の労働環境や人間関係がうつ病の原因である場合には、転職を検討することも一つの選択肢となります。
うつ病の薬物療法は、主に抗うつ薬が中心となります。
抗うつ薬には、SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)、SNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)、NaSSA(ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性薬)など多くの種類があり、脳内の化学物質である神経伝達物質のバランスを調整することで、うつ症状を緩和するために使用されます。
これらの薬は効果発現まで2-4週間程度かかるため、まずは継続して飲み続けることが重要です。
また、抗うつ薬以外に、抗不安薬や睡眠薬も治療に用いられることがあります。
これらはうつ症状に伴う不安や緊張、不眠を改善させる効果があります。
薬物療法だけでなく、対話を通して寄り添うことが力になることもあります。
職場や家庭、対人関係の悩みについて相談などについて、対話を通し、寄り添いながら援助していきたいと考えています。
その際には、認知行動療法やキャリアカウンセリングを始めとした、様々な悩みに応じたカウンセリング(心理療法)を提案していきます。
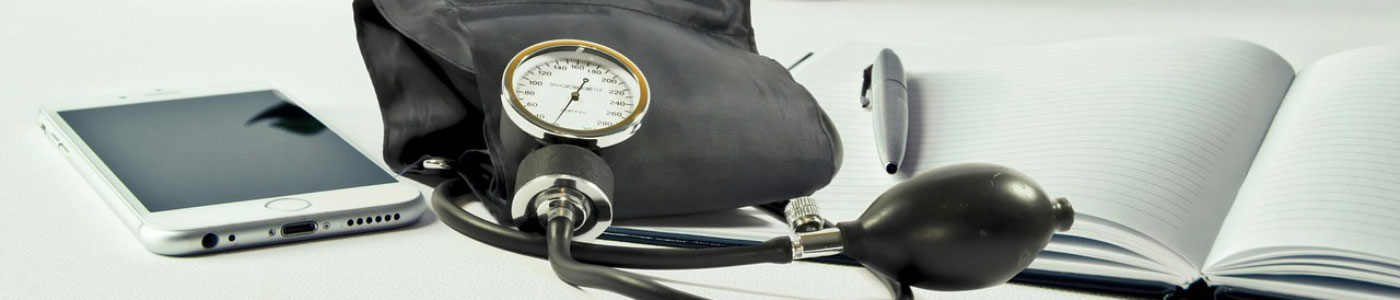
うつ病では、主としてセロトニン、ノルアドレナリン、ドーパミンの3つの脳内神経伝達物質の機能が低下することで、不安、憂鬱気分、意欲の低下、興味関心の低下などの中核症状が出現すると考えられています。
したがって、うつ病で使用される抗うつ薬は、これらの脳内神経伝達物質の機能を高めることによって症状を改善すると考えられています。
具体的にはSSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)、SNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)、NaSSA(ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性薬)といった系統があり、それぞれの系統にも複数の薬があります。
それぞれ効果や副作用のプロファイルが異なっており、うつの症状や程度、合併する不安の程度、不眠のコントロール、食欲の有無、疼痛の有無、年齢、仕事の有無、休職するかどうか、さらには副作用が出やすそうか、薬が続けられそうかなどを総合的に判断して第一選択薬を決定します。
どの抗うつ薬を選択するかはガイドラインである程度推奨されている優先順位がありますが、厳密には決まっていません。
したがって主治医の知識と経験によるものが大きい面も否めません。
逆に言えば、絶対的な優先順位がないということは、第一選択薬が副作用で飲めなかったり、効果が不十分であった場合には躊躇なく第二選択薬を使用すればいい訳です。
登山で頂上に登るルートが複数あっても最終的には山頂に到達するように、多少回り道でも根気よく上り続ける勇気と、それを支える主治医との信頼関係が大事だと考えています。
抗うつ薬の効果はおよそ2−4週間で効果が発現することが多いです。
睡眠薬や抗不安薬と異なり、ゆっくりと効果が現れるため、まずはしばらく継続して内服することが重要です。
副作用の発症は人それぞれで全く副作用の現れない方も多くいますが、頻度の高い副作用には嘔気があり、飲み始めの際は念のため制吐剤を併用していただきます。
副作用の出た方も、しばらく内服していると体が順応し、副作用も次第に消えていくことも多いです。
また副作用の種類や程度も薬によってさまざまですので、個人の体質に合わせて適宜変更していくこともあります。
急性期のうつ症状が改善しても、患者さんが自己判断で抗うつ薬の服用を中止したり、通院をやめたりすることは、薬の中止後症状(退薬症状)や再発につながることがありますのでお勧めしません。
うつ病の患者さんの多くは、いったん症状が治ったように見えても、それはいったん寛解に至っただけで治癒したわけではないので、減薬や中止に際しては必ず主治医と相談してください。
うつ病の再発率は40‐60%という数字もあり決して油断できるものではなく、常に再発のリスクを考慮しながら、薬物療法の継続・減薬の判断をしています。
再発予防のために必要な量の薬を継続服用したり、薬以外の治療法(認知行動療法など)を取り入れながら、診察を通して慎重に経過を見守ることが必要です。
患者さんの中には、再発・再燃の不安から薬に精神依存しやめることに恐怖を感じている方も意外といらっしゃいます。
そのような場合は特に慎重に、患者さんの自己回復力(レジリアンス)や、残存する機能障害の有無や程度、再発のリスクファクターなどを総合的に判断する必要があります。
そして主治医と患者さんが共通の再発のリスクの認識と治療目標を持って、注意深く治療終結の道を探っていくことが求められます。
薬の半減期が長く中止後症状の出現しにくく、また依存になりにくい薬物を治療導入期より選択すること、すなわち出口を見据えた治療薬選択が重要であるのはこのためでもあります。
うつ病治療のゴールは抗うつ薬を含めた薬が全部やめられてうつ症状が寛解を維持していることでしょうか?
最近は「リカバリー」という概念が注目されています。
真のリカバリーとは、症状の回復・寛解が維持されるだけでなく、生活機能の回復、良好な対人関係の実現、仕事や学業における良好な社会機能の回復が得られる一方、患者さん自身がうつ病になって感じた辛さも過去の体験として振り返り、今までのうつ病治療のプロセスを理解して満足していること、その結果ポジティブな思考や対処スキルを獲得している自分に満足していることがうつ病治療のゴールだと考えています。
それにより万が一再発しても(しそうになっても)うつ病の早期兆候に自分自身で気付き、対応できるようになることが期待されます。
以下のような薬の副作用として薬剤性うつ病が発症することがあります。
薬剤性うつ病の可能性が疑われる場合は、一度内服を中止して様子を見る必要があります。
現代社会ではうつ病に罹患する人々が急激に増えてうつ病は身近な問題となっています。当院でもうつ病を始めとした心療内科分野を中心に診療を行っています。
うつ病の治療には高度な医学知識と専門技術を持ったメンタルクリニックによる診療が不可欠です。
一般的にはうつ病の治療というと薬物療法をイメージされる方が多いですが、うつ病は薬物治療のみでは良くならないケースもあります。
当院では薬物療法だけではなく総合的にうつ病を緩和させていく治療を提供しております。
うつ病の中でも、初診時に“うつ”を主訴に来院される患者さんの3割〜4割は躁うつ病(双極性障害)であるとも言われており、その鑑別のためには医療従事者の高度な医学知識や経験が必要です。
当院は各分野のキャリアが長い主治医のもと、メンタルクリニックとして患者さんとの信頼関係を築きながら着実にうつ病を治療していくことが大切だと考えています。
そのためには西洋医療の薬物療法も大事ですが、薬物療法は対処療法としての側面も強いです。うつ病を治していくために漢方薬や運動療法、心理療法、うつ病リワークプログラムなど様々なアプローチを通じた治療を提案・提供しております。
まずは十分な睡眠をとり、脳や身体の負担を軽減することが何より大切です。
もともと、真面目・几帳面・仕事熱心・責任感の強いタイプの方がうつ病が発症しやすい傾向にあります。
このタイプの方は、休養をとるということ自体が苦手であったり、仕事を休むことに抵抗感や罪悪感を持っていたりするため、休まずに頑張りすぎてしまい、ますます脳が疲弊していき症状が悪化してしまいます。
現在も仕事を持っている方には、積極的に休養・休職をすすめます。どうしても仕事を休めないような場合は、仕事量や就業時間を減らして負担を軽くするようにします。
また、主婦の場合は、家事を分担してもらうなど、まずはご家族と協力しながら心の負担を減らすことが大切です。
並行して、薬による治療も行います。(単極性)うつ病の場合は主に抗うつ薬による治療が中心となります。
抗うつ薬は、脳内のセロトニンやノルアドレナリンという神経物質の働きを高めて、抑うつ気分、不安や緊張、焦燥感を取り除くというような効果を現します。
様々なタイプの薬があるので、漢方療法を含め一人一人の症状や状況にあった薬を使います。また、双極性障害(躁うつ病)の場合は、単極性うつ病とは薬物療法が大きく異なります。
従ってうつ病と双極性障害を適格に診断することは、その患者さんの予後を大きく左右することになります。間違った診断を受けないためにも信頼できるメンタルクリニックに通う必要があります。
服薬を含めてすぐに効果が現れるわけではなく、個人差はありますがまずは1週間から3週間の期間が必要です。
通常であれば、2ヵ月から半年くらいである程度うつ病の症状もよくなりますが、その後も継続的に服薬を続けることが必要です。
治ったと思って自分の判断で服薬をやめてしまうと、うつ病の症状が再発してしまい慢性化してしまうおそれもあります。
また、人によっては心理療法も有効です。
メンタルクリニックの信頼できる医師や心理士と相談し、自分に合った薬と治療を見つけることが大切だと言えます。

〒450-6626
名古屋市中村区名駅一丁目1番3号
JRゲートタワー 26F
052-571-7001
休診日:祝日
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15:00~19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
